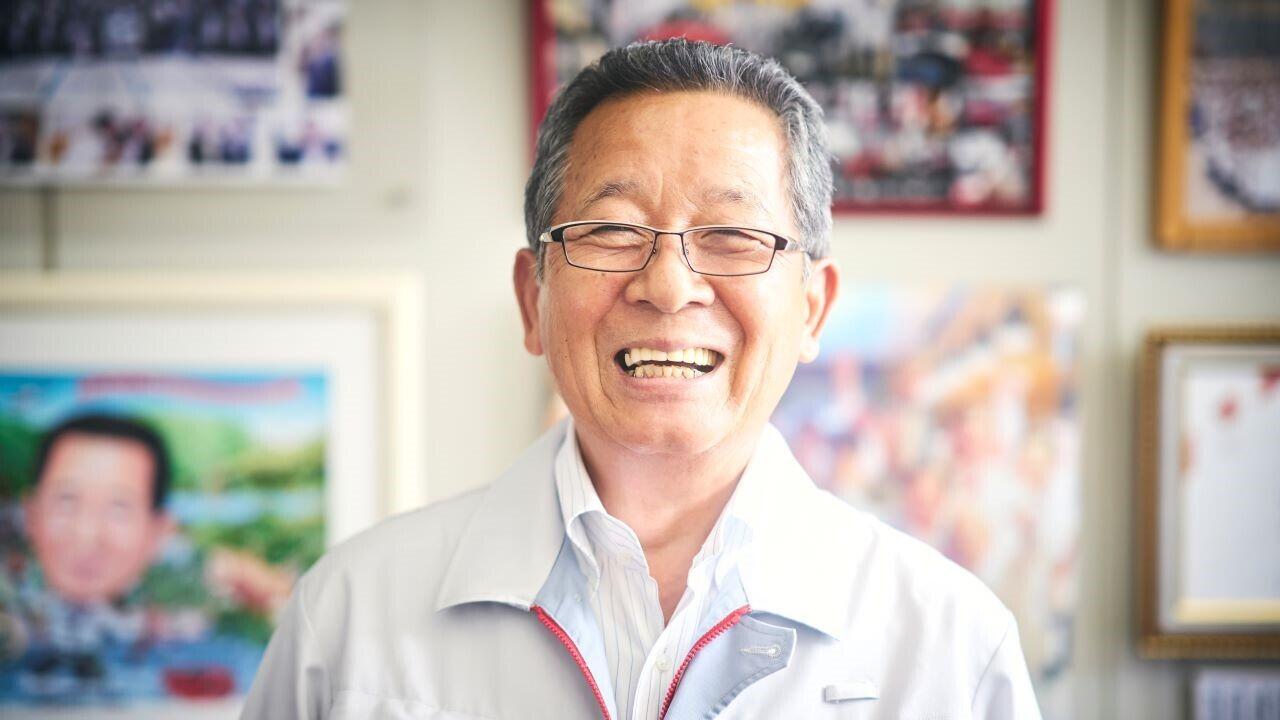
70年以上の歴史がある「創意くふう提案制度」。今回は特別編として、現場一筋62年、製造現場で働く人たちから絶大な信頼を得る"河合おやじ"こと、エグゼクティブフェローの河合満に話を聞いた。
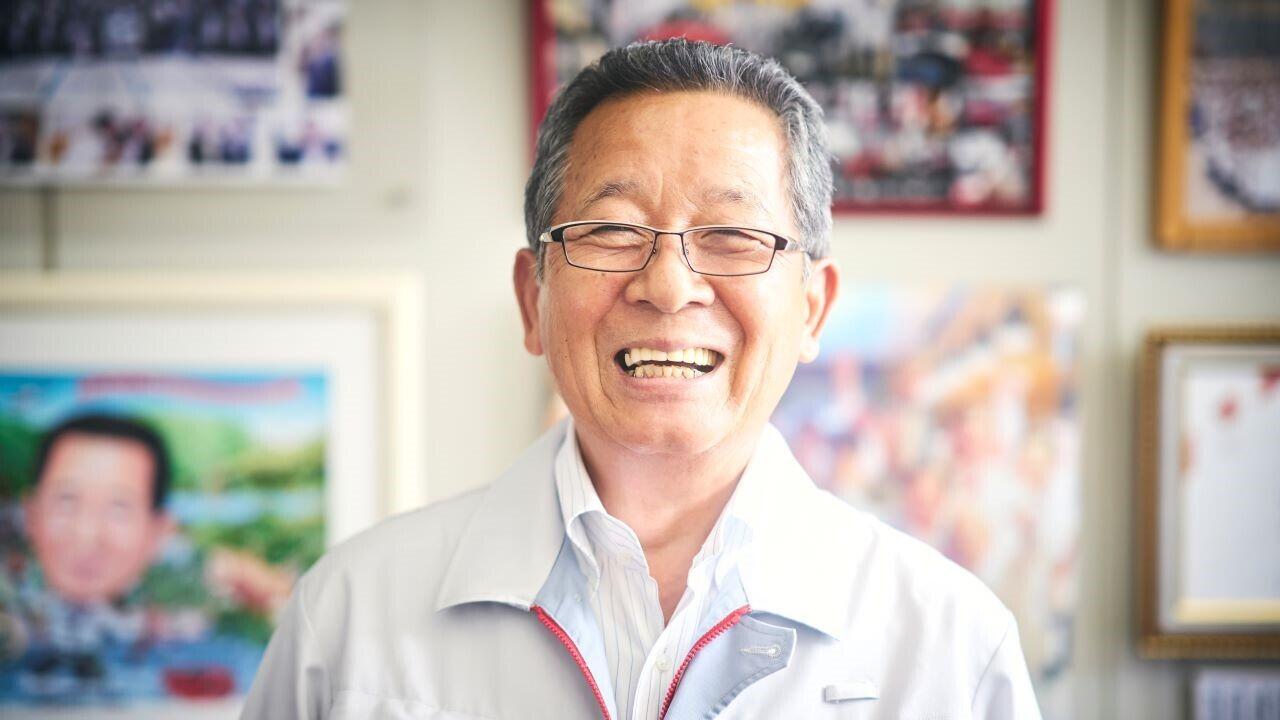
「創意くふうの70年の歴史に関わるところは、河合おやじにもお話しいただくとよいかなと思います」
本連載の立ち上げ時、創意くふう提案制度について、誰に取材したらよいか迷っていたところ、トヨタ社内TQM推進部の担当者からこうアドバイスをもらった。
早速河合おやじに取材を申し込んだが、取材が進むにつれ、残しておきたい、伝えたい話がてんこ盛りに。そこで今回は特別編として、河合おやじの話をお届けしたい。
・トヨタ技能者養成所での最初の教育から、創意くふうをはじめとする改善活動が、トヨタのDNAとして深く根付いていること。
・創意くふう提案制度は単なる制度ではなく、人材育成と密接に結びついていること。
・そしてそれが、現場での実践的な問題解決能力の向上に重要な役割を果たしていること。
・創意くふうは効率化だけでなく、作業者の満足感や達成感につながり、さらなる改善意欲を生む好循環を生み出していること。
・小さな改善の積み重ねが大きな改革に繋がること。
など、60年以上の経験を経て語られた、河合おやじの言葉をお届けします。
創意くふうはトヨタにとって当たり前の原点
河合おやじ
僕は今年で63年目だけど、そもそもは中学を卒業してトヨタ技能者養成所に入ったの。まだ高校じゃない頃ね。その最初の座学で教わったのが、創意くふうの書き方。

当時のトヨタ自動車は、お金もない、設備もない、何もないから知恵を使えってことなんだけど。
創意くふうをすると賞金がもらえて、正しく定量的に書けば評価が上がってお金も上がる。その書き方を先輩が教えてくれる。
通路の出っ張りをなくして、真っ直ぐ歩けるようにするのも創意くふう。そのとき「5歩が3歩になりました」じゃなくて、「1歩が0.5秒だから、計算するとこれだけ効率が上がりました」というように書く。そういうことを教えてくれるんよ。
社内の大きなことは「改善」だけど、そのアイデアは個人が出した「創意くふう」。小さな創意くふうの積み上げで、大きな改善になる。改善なくして改革もない、トヨタ生産方式もない。創意くふうはトヨタにとって当たり前のこと、原点。
賞金よりも嬉しかったこと
若い頃は仲間と競争して(月に)50件とか60件とか創意くふうを書いとったから、残業代よりも賞金が多くなった。賞金目当てもあるけど、一番嬉しかったのは「河合の改善すごい良かった、ラクになったよ」と仕事仲間に言われたこと。

当時昼勤の私が何かしら改善すると、夜勤の人がそれを実践することになる。その感想を聞きたくてワクワクしながら会社に行ったね。でも、自分が工長になると、昼休みも家でも競争するように部下が提案を書いとるから採点するほうは大変。(笑)
昔、職場を家族に見せましょうっていう日をつくったんだけど、指が不自由な従業員の奥さんが来て、「ここの焼結摺動はどういうことなんですか?」って言うわけよ。その従業員も他の人と同じ仕事を全部やっとった。
びっくりして「奥さんなんでそんな専門用語知っとるの?」と聞いたら、旦那さんが家でビールを飲んでる間は暇だから、奥さんが創意くふうのシートを(代わりに)書いとったんだって。そんで賞金を夫婦で分けとったらしい。
そのうち専門用語を全部覚えちゃって、奥さんは「酒代は創意くふうで稼ぎなさい、私は作業代をもらうから」って。奥さんもそれが楽しみだって言うんよ。そんなこともあったね。(笑)
実は横着者のほうができる!?
部下を持つとわかるけど、創意くふうに熱心な人は伸びる。それだけ問題意識を持っとるわけだから。あと、創意くふうは横着者のほうができる。いかにラクにやるか、早く終わらすためにはどうしたらいいかを考えるから。

いい加減にやると横着だけど、ちゃんとやって早く終わらせるには、ものすごく考えんといかん。言われたことだけをやっとると知恵が湧かんでしょ。
言われたことだけをやっとったら、こんなつまらんことないからね、一番の苦痛。
「当たり前」とか「昔からそう決まっとる」っていうのは、改善しない人たちの言葉。
子どもの「なぜ? なぜ?」に、「うるさいだまれ!」って答えるのと同じ。だから、新人のほうが「なんであんなことしとるんだろ?」って気づくこともある。
わからなければ聞く。前・後工程に行って聞くとか。そういう人は伸びるし、部下も憧れる。それが教育。

大事なのは上司の姿勢
でも、若い子は難しい改善なんかできない。書類をあっちからこっちに持っていく手間を少し改善するような(小さな)提案だとしても、「いいね!」って上司はちゃんと受ける。そういう姿勢を示さんと案を出さなくなっちゃう。
失敗しそうだなと思っても、一回やらせてみる。僕はNOって言ったことはほとんどない。誰が何を言ってきても、「いいじゃないか、やってみなわからん!」って。

最近はおとなしい子が多いとか言うけど、エネルギーは昔の人も今の人も変わらんから。そのエネルギーをどう生かしてやるか、どうやって仕事を面白くさせてやるか。そのためには改善して、みんなで喜んだり、達成感や満足感が得られるようにしてあげる。
そういうことがトヨタの現場のDNAでもあるし、続けていくことが大事。
能率・生産性の数字の意味
ラクになって早くできると、結果的に生産性が上がっていく。決して労働強化でやるわけじゃない。トヨタ生産方式って聞くと、能率で縛られる、生産性をすごく言われる、と思われるけど、あれは数量を言っているんだけど数字だけの話じゃない。あれは改善をして、「ここまでもっていこうよね」ということ。

例えば「今年は生産効率103%向上」という目標が出たとする。その課に100人おったら、3人減らして、97人で仕事をすれば、生産性が上がったということ。そのときに、97人でやるにはどうしたらいいかを考える。慌ててやるんじゃない。
「3歩歩くところを2歩でやれるようにしよう」
「3人で一つのことやっとったら、2人でできんか」
「重くてできんから、じゃあアイデアだしてカラクリ使って簡単にやろう」
「カンコツ(勘とコツを)使わんとやれんところも、簡単にできるように案内つければいい」
そういう小さい改善をずっとやる、改善の目標指数みたいなもの。先に生産性が何%じゃなくて。3%あげるには、3人いなくてもやれるようにするには、どうしたらいいか。
最初から人をラクにするとか、そういう目的でやらないと。能率だけ上げたり、会社の原価低減のためにちゃんと改善しようというと、無理なことが起きちゃう。そうじゃない。自然に改善すること。
例えば、新人が標準作業でいつも膝を汚しとる。「なんで汚れるの?どこで汚れるの?」とヒントを出す。すると、取り付けの時に必ず膝を当てることに自分で気づく。一つひとつの仕草でやりにくそうなところにも気づく。それを取り除けばもっとラクになる。
そういうヒントを与えると、自分でも改善するようになる。
そういう改善を、職場の中でどんどん、人が入れ替わっても、次の人が同じことができるように(やっていく)。これがどんどん繰り返しやられて、立場が上がったり、範囲が広がったりいろいろな仕事やっとると、その分だけ(効果が)大きくなるわけ。
創意くふうを軸に、ひろがり続ける改善の好循環
土台の部分には、一人ひとりの創意くふうがあって。その次に、もう少し大きなことをQCサークル(創意くふうの小集団改善活動)で改善して課題解決をしていく。
創意くふうをやってると、コミュニケーションが生まれる。先輩から「もうちょっとこうせいよ」、上司からは「そこまでできたなら、こっちもできるんじゃないか」って。
トヨタには「改善後は改善前」という言葉があるけど。改善したら終わりじゃなくて、そこからどんどん転がって大きくなっていく。

外部のいろんな人から、「なんで全員がそんなに改善できるの?」って言われるんだけど、答えようがない。僕らはそれが当たり前の世界におるから。でも、その感覚で外部の人に言っちゃうと失礼になることもある。
講演に呼ばれたり、工場に伺うこともあるけど、「無駄なことやっとるな」ではなく、「一緒にやりましょう!」ってやってみる。そうするとすごく良くなる。 向こうの人が気づくようになる。
改善って「こんなちっぽけな、こんな当たり前なことやるだけでいいのか!」って気づいてくれれば、自分たちでもできると思うようになる。
改善はみんなが喜ぶし、みんなが驚いてくれる。そうするともっとやりたくなるし、仕事のやりがいになる。みんながラクになって効率も上がるんよ。
一番印象に残った創意くふうは…
これまでに印象に残った創意くふう?そんなん言い出したらキリがない。
工場に行くと常に進化しとるんだから。行くたびに「おやじ見てくれ!」ってみんな得意になって見せてくる。みんな自慢したくて仕方がない(笑)。でも、本当によく考えられとるし、行くたびに驚かされるんよ。
いつの時代も状況や環境は常に変わるけど、そういうときこそ創意くふうが効いてくる。

自働化をするにしても、手作業を徹底的に安全に、品質が良くなるまでやらんと。手作業で工夫して、誰がやってもできるようになったらロボットにやらせればいい。それまでは自働化しちゃダメ。
難しいことを自働化すると、センサーだらけで複雑になる。複雑になるとブラックボックスになるから故障しても自分で直せない。メーカー研修に行って3ヶ月学んでも、1年もすれば新製品がまた出よる。
AIにしても、誰が教えるの? という話。塗装も溶接も、ロボットよりうまい技能の人を呼んできてその技術を移植する。下手くそな字を書くやつが教えたら、ロボットも下手くそな字を書く。達筆の人が教えると達筆になる。
AIが全部やるようになったら、競争力もなくなる。だったら、もっと効率を上げることを教える人がおらんと。みんなが3台で1個作るなら競争力はない。それを2台でできるようにするのが改善。1台で無理なら2台で生産を倍にすればいい。だからキリがない。
繰り返しになるけど、改善なくして改革もないし、トヨタ生産方式もありえない。自分が成長できたのも、そういう改善魂。創意くふうの土台があったから。

